お知らせ
第53回研究会について
| 日時 | 2026年 3月 10日(火)13:10~16:50 |
|---|---|
| テーマ | 『 環境とロボティクス ~極限のフィールドから社会インフラまで 実世界に実装される自律システム~ 』 |
| 開催形式 | ハイブリッド形式(現地参加またはオンライン) (現地参加) 上限30名・先着順 TKP東京駅カンファレンスセンター11階カンファレンスルーム11D → アクセス方法 (東京都中央区八重洲1-8-16 新槇町ビル11階) (オンライン)上限350名・先着順 Zoomウェビナー |
| ※ 参加申込URL ※ | https://forms.gle/RHvuDbE9yptwRjBk8 |
| ※定員上限を超えた場合、お断りさせていただくことがありますので、ご了承ください。 ※お申し込みは参加者ご本人様にてお願いいたします |
|
| プログラムPDF | HAS研第53回研究会プログラム |
近年、デジタル空間でのAI活用が急速に進む一方で、物理的な「実世界」の変動や不確実性に適応するロボティクス技術への期待がかつてないほど高まっています。そこで、今回の研究会では『環境とロボティクス ~極限のフィールドから社会インフラまで 実世界に実装される自律システム~』というテーマを掲げ、本分野の最前線でご活躍されている皆様にご講演をいただくことになりました。
建設現場や農業分野でのロボティクス活用、そして身体性を持つAI(Embodied AI)への進化について理解を深めるとともに、社会実装の在り方について議論する貴重な機会になればと考えております。皆様方におかれましては、ぜひお申し込みいただき、ご予定いただけますと幸いです。
参加お申し込みは上記のURLからお願いいたします。また、会終了後にささやかながら立食形式による意見交換会を開催いたしますので、ご参加をご希望される場合は、同じフォームURLにてお申し込みをお願いいたします。(参加費は無料です)
プログラム(敬称略)
開会挨拶 (13:10~13:20)
『SIP スマートインフラ サブ課題A『土工事の自動施工技術』の研究開発のご紹介と社会実装に向けた取り組み』
(講演 13:20~14:00)
労働力不足が深刻化する中、建設現場では省人化と生産性向上が強く求められており、土工事における自動施工技術への期待が大きく高まっています。一方、自然環境を対象とする土工事は、環境条件が多様であるため、自動化技術の実工事への適用は、まだ十分に進んでいません。そこで我々は、土工事の自動化を目指した技術開発と、技術の社会実装に向けた取り組みを推進してきました。
本講演では、この自動施工技術の概要に加えて、社会実装に向けた方策を紹介します。本講演が、皆さまの技術の社会実装を進める際のヒントとなれば幸いです。

講師
永谷 圭司
筑波大学 システム情報系 教授
プロフィール
1997年 筑波大学大学院博士課程修了。博士(工学)。カーネギーメロン大学 機械工学科(ポストドクトラルフェロー)、岡山大学 大学院 自然科学研究科 講師、東北大学 大学院 工学研究科 准教授、東北大学 未来科学技術共同研究センター 准教授、東京大学大学院工学系研究科 特任教授を経て、現在、筑波大学 システム情報系 教授。SIP 「スマートインフラマネジメントの構築」 サブ課題A の研究開発責任者。フィールドロボティクスの研究に従事。日本ロボット学会、計測自動制御学会、日本機械学会、土木学会、IEEE等の会員。著書:「不整地移動ロボティクス(編著)」。
(休憩 10分)
『AI・ロボットを基軸とする農業DXの未来』
(講演 14:10~15:00) -リモート講演-
農業は私たちの生活と命を支える人類生存に必須の営みであり、その持続性を確保するために技術革新が強く求められており、スマート農業技術の研究開発は世界的に活発に行われている。今後のスマート農業は農業支援サービス事業者が利用できる高度な技術である必要がある。ロボット農機は自動化から知能化に進化し、これまで以上にデータの利活用が重要になる。
本講演ではリモート農業、AIロボット、デジタルツインなど次世代スマート農業の姿を論じる。
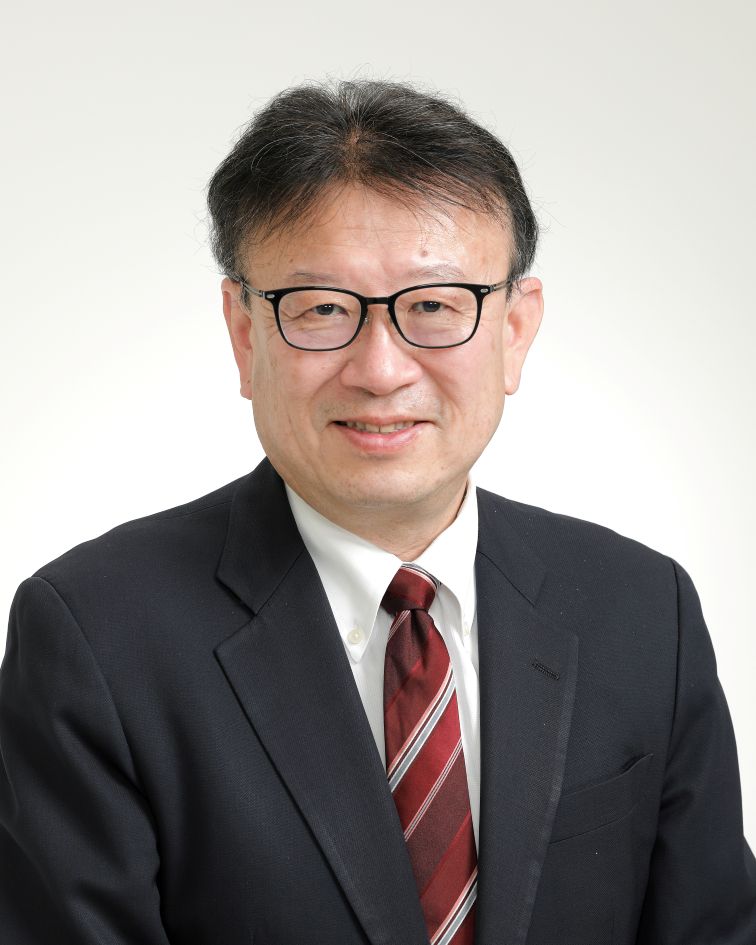
講師
野口 伸
北海道大学 大学院農学研究院 研究院長・教授
プロフィール
1990年北海道大学大学院博士課程修了。農学博士。1990年北海道大学農学部助手、1997年助教授、2004年教授。2023年農学研究院長(現在に至る)。この間、日本学術会議会員(第20~22期)、日本学術振興会学術システム研究センター専門研究員(2006-2009年)、内閣府戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第1期「次世代農林水産業創造技術」プログラムディレクター(2016-2019年) 日本農業工学会会長(2021-2024年)など歴任。農業ロボットなどスマート農業に関する研究に従事している。近著に「スマート農業の基本」(誠文堂新光社)がある。
(休憩 10分)
『現場作業の自律動作能力を拡張しEmbodied AIへと進化するロボティクス』
(講演 15:10~15:50)
製造業、物流、建設業、インフラ保守現場における労働力不足と生産性向上は喫緊の課題となっています。この解決策として、現場で人間と安全に協働できるAIロボットへの期待が高まっています。同時に、Physical AIやロボット基盤モデルへの注目が高まっており、多様な汎用タスクを自律的に実行するAIが急速に進展しています。
本発表では、これらに関連する日立のAIロボットへの取り組みを紹介するとともに、AIの進化をEmbodied AI、すなわち身体知を持つAI の方向性で捉えて、その将来展望について述べます。

講師
野口 直昭
株式会社日立製作所 研究開発グループ Digital Innovation R&D
モビリティ&オートメーションイノベーションセンタ
プロジェクトマネージャ
プロフィール
1999年日立製作所に入社。昇降機の制振、耐震、駆動に関する研究開発に従事。2007年度 日本機械学会奨励賞受賞。2019年から2024年まで、研究開発グループ ロボティクス研究部部長を務め、フィールドロボット、サービスロボットなどの研究マネジメントに従事。2024年より内閣府・ムーンショット型研究開発(目標3)「一人に一台一生寄り添うスマートロボット」研究テーマにおいて、課題推進者(PI)として本プロジェクトを推進。日本機械学会関東支部役員、日本ロボット学会理事などを歴任。博士(工学)、日本機械学会会員、日本ロボット学会会員、IEEE会員。
パネルディスカッション (16:00~16:30)
総会 (16:30~16:40)
閉会挨拶 (16:40~16:50)
意見交換会(現地参加のみ) (17:00~18:00)
-
-
2025年3月11日
-
2024年10月25日
-
2024年3月19日
-
2023年10月4日
-
2023年3月15日
-
-
-
2022年9月26日
-
2022年3月29日
-
2021年5月31日
-
2020年11月4日
-
2019年9月26日
-